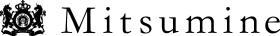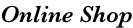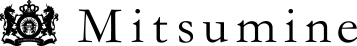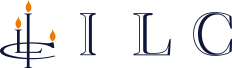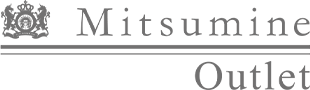仙台泉プレミアム・アウトレット店
気分はペイズリー♪
ネクタイの柄とは不思議なものである。
とりわけゾウリムシや勾玉が連続する様なペイズリー柄のネクタイが何ゆえにスーツにコーディネートして成立するかは予備知識の無い者に取っては不思議な光景だろう。
いつもブログをご覧頂きありがとうございます。
Mitsumine仙台泉プレミアムアウトレット店です。
私がペイズリーのタイを初めて意識したのは30数年前の入社したての頃。
当時菱屋という大手のネクタイブランドのプリントのペイズリー柄が入荷していました。
新参者ではありましたが、こんなダサい(今は死語?)柄は誰がするのだろうと感じながら、いつしかペイズリー柄を長い間避けてきたような気がします。
そんな私でも社歴が30年を越えて、数多くのネクタイを締めてきました。その中で4本だけペイズリー柄のネクタイを見つけました。
そのMitsumineアーカイブを簡単に紹介します。

※1990年代に初めて買ったペイズリー柄のタイ。フランスブランドのブリュワーとMitsumineのダブルネーム。
クールな色出しが気に入っていました。

※2000年代初頭の頃に買ったイタリア老舗ブランド、フランコ・バッシとMitsumineのダブルネームの大柄ペイズリーのタイ。夜の街が似合いそうな色気があるタイです。

※これも2010年代頃のMitsumineイタリーのオリジナルタイ。この頃からソリッドタイのトレンド傾向があったので、ブラウンのペイズリーソリッドタイは当時新鮮な感じがしました。

※2020年代に買ったcotton&silk混紡のMitsumineイタリーのオリジナルタイ。ベージュのソラーロのスーツにコーディネートするタイとして買った春夏向けの大柄プリントのペイズリータイです。
ペイズリー柄のたった4本のネクタイにも改めて振り返っても、確かな自分のオリジナルストーリーがあるようです。
それともペイズリー柄だったから印象が残ったのかも知れません。
そもそもペイズリー模様の意味とは?
インドのカシミール地方の伝統的な模様という説もあり、起源は定かではありません。
18世紀にヨーロッパに伝わり、スコットランド西部の「ペイズリー」という町でその柄の織物が大量生産されたことからペイズリーと呼ばれるようになったとのこと。
ペイズリー模様はゾウリムシなどの原生動物、植物の種子・胞子・果実、花弁、菩提樹などの葉などの曲線のモチーフと草花などの柄がリズミカルな連続した規則的な配列によって、原初の生命力の躍動感を印象付け、人間の心理に安心感を与える効果があるとも言われています。

※英国制のペイズリー柄のポケットチーフ(筆者私物)
チーフやスカーフにするとペイズリー模様の印象も英国調やオリエンタル文化の融合、シルクロードをも連想させる雰囲気がありますね〜
かつてフランスの歴史的英雄、ナポレオン・ボナパルトもこよなくペイズリー模様を好んだとか。
フランスがペイズリー模様の先進国になったのもナポレオンがそのデザイン開発を推進したためとも言われています。
ペイズリーは伝統的な歴史ある模様で、古くから世界中で多くの人々に愛されているパターンだからこそ、ネクタイの柄としてスーツにコーディネートしても違和感なく存在感があるのでしょう。
ペイズリーは奥が深い・・・
私も50代後半の年齢になり、いつもお客様にとって刺激的なファッションをするように心がけてきましたが、そろそろ落ち着いた装いと安心感を与えるペイズリー柄のネクタイを締めようかと少々考えております(笑)
取り急ぎこの「ペイズリー」という柄の意味を掘り下げる機会にショーウィンドウにもペイズリー柄のネクタイをディスプレイしてみました。



ペイズリー柄ネクタイ ¥8,800→¥6,600(税込)
※大柄のヴィンテージ調のペイズリー柄、前回のブログで色違いのグリーンも紹介しています。

ペイズリー柄ネクタイ ¥8,800→¥6,600(税込)
※レジメンタルxペイズリー柄の珍しいパターン、お店では大人気のタイです。色違いでグレー、ネイビーの3色展開。
お店にはまだまだ紹介していないペイズリー柄のネクタイがございます。
貴方にピッタリの落ち着いた大人の印象を与えるペイズリーを探してみませんか?
振り返ってみればそこには人生のストーリーがあるはずです。
スタッフ一同そのお手伝いをさせて頂きます。
ご来店を心よりお待ちしております。
最後までこのブログをご覧下さり、ありがとうございました。